学校での怪我、けんか、いじめ等のトラブル発生時には、事実関係を確認して指導をします。保護者に連絡もします。
なのに、その後に保護者がモンスター化し対応が泥沼化することもあります。
対応のポイントをまとめます。
映像レベルでイメージできるように
トラブル発生時には「時系列」で事実を確認しますが、大体のストーリーのみを聞き取った程度であることが多いです。
「校庭で6年生の投げたボールが頭に当たった」「6年生は謝った」「保健室に行かせた」この程度では事実確認や対応が甘いのです。
・校庭のどこか
・どんな種類のボールか
・上から振りかぶって投げたのか下から軽く投げたのか
・どれくらいの距離からか
・謝ったときの口調や様子はどうだったか
・保健室ではどのような手当てをしたのか
・担任はどのような対応をしたのか
場面を映像で見るようにイメージできることが重要です。
事実確認とはそのレベルです。
事実確認の詳しさが対応の丁寧さに
ボールの投げ方や距離によっては、危険度や痛さの度合いが違います。
謝り方も近づいてきて「心配そうに」謝ってくれたのか、遠くから「儀礼的に」言葉を発しただけかによって、反省の程度も違います。
6年生の誠意が本人に伝わっていなかったら、教員が間に入り改めて謝罪させる必要もあります。
保健室で冷却材を借りて30分ぐらい冷やしたとか、1時間後に「大丈夫か」と声かけしてその後の無事を確認したとか。
そこまで丁寧に対応すると、子どもの安心につながります。
子どもの気持ちを安心させて下校させると、子どもは親に「6年生にわざとボールをぶつけられた」などと悪意が連想できる報告にはなりません。
「詳しく正確」が親への説得力に
子どもの伝え方が不正確であったり、親の先入観が強かったりして、家庭で学校での出来事が正しく伝わっていないことがあります。
そんな時に、担任からの連絡の内容が子どもの言うこと以上に「詳しく正確」だったら、それが説得力になります。
親の先入観も解消されます。
「詳しく正確」な事実確認は手間がかかるようですが、後々問題を深刻化させないために重要なことです。
まとめ
「詳しく正確」な事実確認を迅速に行うには、教員の聞き取る姿勢も重要です。
・苛立った表情をしないで共感的に聞く
・質問を挿入しながら正確に聞く
・近くにいた子の話も総合して聞く
生身の子どもが生活する学校では、不測のトラブルが多発します。
1つ1つに的確に対応して問題を必要以上に深刻化させないようにしたいです。


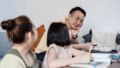
コメント