小学校教員にとって不人気な教科が社会科です。
「覚えることが多すぎる」「教え方が分からない」・・・。
しかし、実は、社会科は最も日常生活に密着した教科です。
教員は是非とも社会科を学ぶ意味をしっかりと理解したいです。
社会科の学力というと何をイメージするでしょうか。
都道府県や県庁所在地の場所や名称、歴史上の人物や出来事や年号の知識でしょうか。
あるいは、山脈や河川や気候の知識でしょうか。
それらも社会科の学力と言えます。
しかし、それらを覚えていなくとも、日常生活では特段の不自由はないかもしれません。
私は社会科の学力とは、もっと身近に使いこなしているものと思います。
社会科で育てたい力を、ズバリと簡単に言うならば次です。
より良いくらしを営む力
私たちは快適で安全で健康なくらしを実現するために、様々なことを工夫したり考えたりしています。
例えば、お出かけ前にテレビやネットで天気予報を確認します。
それによって、服装や履物、持ち物を決める場合があります。
花粉情報によっては、目薬や点鼻薬をバッグに入れます。
誰しも気候や気象から強い影響を受けて生活しています。
通勤電車に事故による遅れが発生したら、電車内や駅の案内を聞いて、振り替えルートを探して移動します。
従って、交通や地理と無縁な人はいないわけです。
また、私たちは仕事をして生計を立てています。
製造業やサービス業など様々な産業の担い手になっているわけです。
また、欲しいものをネットで注文したり物を宅配で送ったりしています。
通信や流通を使いこなして生活しています。
さらに、私たちはより良いくらしを実現するために、選挙で代表を選んで世の中のルールを作っています。
それが政治といえます。
そう考えると、私たちは、社会科の力をいつでも使って生活しています。
小学校における社会科の学力は、1・2年生においては生活科で育まれます。
学校、家族、学校の周りという具合に子どもたちの身近なところから学び始めます。
3年生になると市区長村、4年生になると都道府県と学習の範囲が広がっていきます。
5年生では日本全体の地理や産業に学習が及び、6年生では歴史、世界という視点でも学習していきます。
政治、経済、世界、歴史・・・となると、学習対象は、もはや無限と言えます。
だから、何でもかんでも暗記すべきものと考えると、誰だって嫌になってしまいます。
「より良いくらしを営む力」は、知識だけではありません。
むしろ「なぜだろう?」という素直な疑問や興味こそが、最も大切な学力だと思います。
その「はてな?」を子どもたちと共有できると、社会科好きな子どもが育ちます。
そして、検索したり、人に質問したり、現地で確かめたりして、「はてな?」が解決されて、また新たな「はてな?」が生まれます。
それこそが、社会科の面白いところであり醍醐味といえます。
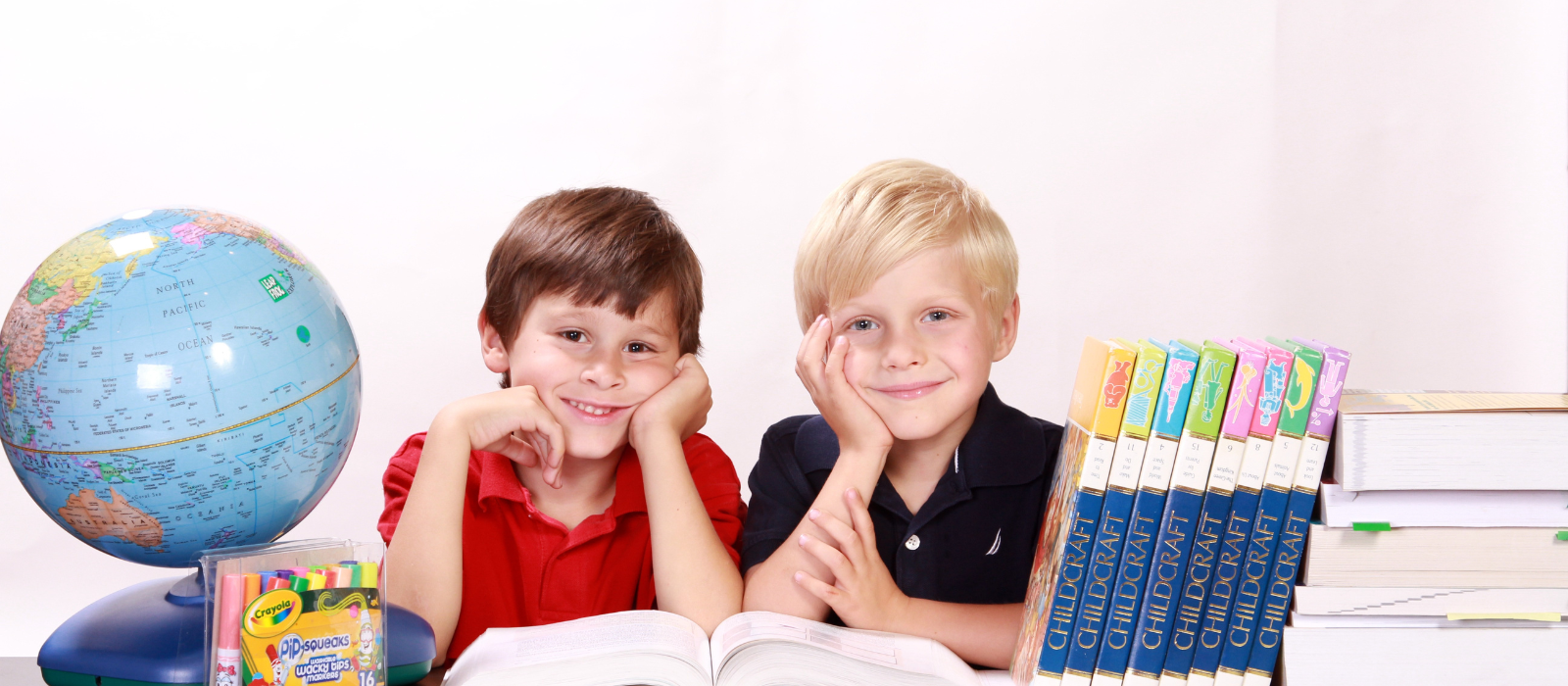


コメント