保護者は我が子がいじめられることを何よりも心配しています。
しかし、いじめは「いつでも、どこでも、誰にでも」起こり得ることです。
大切なことは、早期発見と早期対応です。
校長は学校便り等で、いじめに対する学校の本気の覚悟と具体的な対策を明確に語りたいです。
======================
Aさんのお母さんから次のような相談があったとします。
「子どもに元気がありません。‟学校に行きたくない″と言っています。Bさん達から無視されているようです」
いじめかもしれません。
学校では、Aさんに辛い思いをさせていることとお母さんにご心配をおかけしていることをお詫びします。
そして、早急に事実関係を調べたり当事者に指導したりして、改めて学校から報告をすることをお約束します。
そして、翌日には関係する子どもに事実確認します。
通常は、AさんとBさんには、別々に聞き取ります。
その他の友達も関与している場合には、同様に個別に聞き取ります。
いじめの可能性がある案件では、関係者を一堂に会して、話を聞くようなことはしません。
子供たちがお互いの顔色を気にして、無言の制約がはたらく恐れがあるからです。
もし、苦しんでいるのがAさん1人で、Bさん達大勢が明らかに非道な仕打ちをしていたら、当然、厳しく注意をして謝らせて、二度と同じことをしないように指導します。
しかし実は、そういうパターンはごく稀です。
状況はもっと複雑であることが多いです。
その出来事から数か月前に、逆に、AさんがBさんに対していじめをしていることがあります。
あるいは、Aさんの心無い言動が多くの友達の不満として鬱積しているケースもあります。
そのような場合は、Bさん達の気持ちにも寄り添わないと解決になりません。
両者にそれぞれ別のデリケートな指導が必要です。
Bさん達もAさんに対して苦しんでいる場合もあります。
そこで、Bさん達には次のように指導します。
「君たちはAさんのそういうところがずうっと嫌だったのですね。確かに、それは嫌だったね。そこには同情できるよ。Aさんには先生から、君たちの思いも伝えて注意します。でも、今回は、君たちがAさんをいじめたのです。素直に反省できますか。だったら、今回のことは、君たちが、Aさんに謝ろうね。」
通常は上のような指導でBさん達は、素直に反省します。
Aさんも教師の指導を受け入れます。
そして、Aさんのお母さんには、事実関係と指導の経緯を詳しく報告します。
関係者の話を公平に聞き、事実関係を把握する。
そして、子どもたちの思いを受け止めた上で指導する。
そのように一つ一つの問題を乗り越えて、どの子も安心して過ごせる学校生活を実現する。
それが、学校の果たすべき役割と考えます。
6月は「ふれあい月間」です。いじめの未然防止、早期発見、早期対応に力を入れる取組です。
学校では、「STOP!いじめ」「SOSの出し方」などのDVDを視聴させます。
「生活アンケート」で問題の掘り起しを図ります。
思春期を迎える5年生には、スクールカウンセラーによる全員面談を実施します。
全教職員で、あらゆる側面から子どもたちの人間関係を見つめ直します。
「いじめは、いつでも、誰にでも起こり得るもの。大切なことは、早期発見と早期対応」
という認識で臨んでいきます。
お子様の様子でご心配なことがありましたら、どうぞ、いつでも学校にお知らせください。
お子様の気持ちを大切にしてスピーディに丁寧に対応していきます。


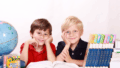
コメント