「はっきり言って面倒くさい評価の話は嫌い」という教員は多いと思います。
これなら現場の教員の腑に落ちる。
そんな評価の考え方と方法を紹介します。
真面目過ぎる非現実的な話は抜きにして。
評価には3種類あるがそもそも別物
1つめは「成績付けの評価」です。
「ABC」「321」等で示す通知表や点数化して合否判定する入試が該当します。
2つめは「指導改善の評価」です。
教員が自分の指導をよりよくするために行います。
3つめは「学習調整の評価」です。
子どもたちが自分の学習活動を見直す評価です。
一口に評価と言っても、これら3つの評価には関連はありますが、営みとしてはそもそも全くの別物と整理すると頭がすっきりします。
「成績付けの評価」のポイントは点数化
成績付けだから段階付けができるように点数化すべきです。
「知識・技能」については授業後や単元末などに定着度を全員一律のテストで評価します。
「思考・判断・表現」については、単元末テスト以外にも学期に1~2回でもいいので評価の機会を設定します。
社会科だったら学習新聞、理科だったら実験のまとめなど、ある程度その子の個性が表れる成果物を成績に加味します。
作品からの見取りであっても、評価の観点や基準を設定して点数化することが重要です。
「成績付けの評価」は、無理して多くの評価場面を設定する必要はありません。
「こんな方法でこんな結果だったからこの成績です」と説明できることが大切です。
「指導改善の評価」はゆるくていい
「形成的評価」とも言います。
教員は「学習のねらいが達成できたか」「指導は効果的だったか」というアンテナを働かせます。
「しまった!」と思ったらすぐに授業中に軌道修正をします。
「この指導は上手くいった」と感じたらその後も採用してみます。
「指導改善の評価」は無理のない範囲でゆるくてかまいません。
しかし、机間指導の際にポイントとなる子どもの活動をチェックしたり、子どもたちの表情やつぶやきをとらえたりして、指導改善のアンテナは常に働くようにしたいです。
「学習調整の評価」は研究していきたい
これも一種の「形成的評価」ですが、子どもたち自身が行う評価です。
個別最適な学びや探求学習を成立させるためにも、子どもたちの自己調整力を育てます。
「何のための活動か」「自分はどこまで到達しているか」「これからどうするか」を判断できる力です。
ワークシートや黒板に「ねらい」と「評価基準(ルーブリック表)」を常に示しておきます。
活動前、活動中、活動後にいつもそれらを確認して、「〇△×」等で自己診断させます。
初めのうちは、教員の指導の下で学級全員で丁寧に確認します。
少しずつ一人一人が自立してできるようにします。
「学習調整の評価」は学校の研究推進の一環として組織的に取り組んでいくことが理想です。
まとめ
よく研究授業の指導案に「評価規準」をきちんと示すことが求められます。
そもそも研究授業は、「指導改善を目指した試み」です。
だから、「指導改善ための観点や場面」を強く意識して授業に臨むことが大切です。
しかし、普段の授業における評価については、できる範囲の心がけでよいのです。
それが現実というものです。


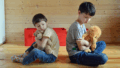
コメント