絵本の読み聞かせでは、赤ちゃんは言葉を耳で聞き、絵を見て理解し、文字を目で追い、時には意気に入りのセリフを繰り返します。
「聞く」「読む」「話す」能力をバランスよく使います。
奥村優子氏は「赤ちゃんは世界をどう学んでいくのか」(光文社新書)の中で、乳幼児期の読み聞かせの利点を分かりやすく紹介しています。
共同注視が学習やコミュニケーションの土台となる
読み聞かせの場面では、赤ちゃんが養育者などと一緒に対象に注目します。
それを「共同注視」といいます。
同じページを見たり、絵について話したり、思いや感情を交流させたりします。
共同注視に心地よさを感じられるようになると、それが学校の先生や友達との学習や活動にも自然に移行していくことが期待されます。
日常の遊びとは異なる言葉のやり取りを生み出す
絵本を読んでいると、養育者の発話が長くなり、物の名前を覚える機会が増えます。
子どもの発話に対して、養育者がしっかりと応じる傾向も強くなることも研究で示されています。
こうしたやり取りが、子どもの言語発達を後押しするといわれています。
豊かな語彙や多様な表現を育てる
日本語の日常会話では、「~は」「~が」「~を」などの助詞が省略されることがよくあります。
絵本の文章では助詞がきちんと使われることが多いです。
子どもは正確で豊かな言葉に触れることができます。
絵本の特長が、子どもの語彙力や文法能力の発達を支えます。
子どもの道徳心を育てる
絵本は子どもを楽しませるだけでなく、友情や信頼、責任感、正直であることの大切さなどを伝える手段としても、世界中で広く知られています。
私たちは日常生活での経験以外の多くの架空世界からも、人として大切な道徳心を育んでいます。
まとめ
絵本は子どもにたくさんの言葉を届け、言語発達や情操教育を支える重要な役割を果たします。
親子のコミュニケーションを深める手段としても、絵本は欠かせない存在といえます。
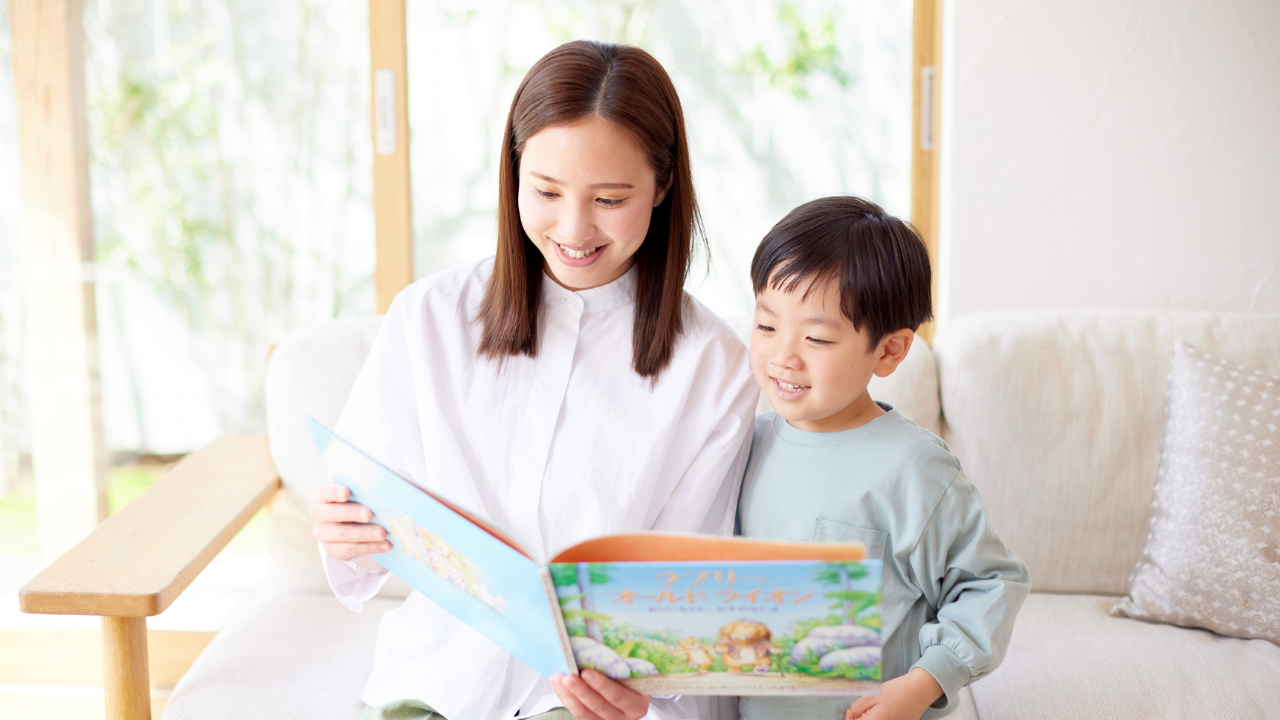


コメント